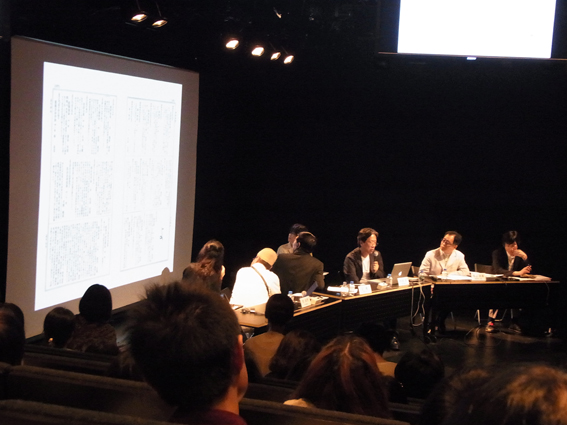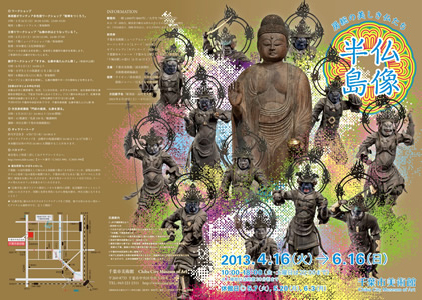【以下、長文】
当初はもっと人数が多い予定だったのだが
仕事が忙しい人、腰がイカレた人、前日に体力が0になった人、
二日酔い(予想)の人、寝坊した人……などなど多種多様の理由で
KC嬢と二人でランデヴー登山(ランデヴーの使い方が違う)。うふふのふー。
降り立った奥多摩は「なんじゃこりゃーーーー!」と叫ばざるを得ないくらい混雑していて
一体なにがあったのかと思う。これがアレですか、登山ブームってやつですか……。
こんなの初めて見たなぁ。バスは1台では到底足りず、多分4台かそれ以上出たはず。
当然、登山口も「うわー」という人だかりだった。
しばらくは舗装道路なので、よもやま話をしながらのんびり登る。
川沿いは涼しくて空気もさわやかで「いいねー」「気持ちいねー」とにんまり。
ここはいいぞ、という予感がこみ上げてくるのであった。
夏に向かって樹々は元気に葉を茂らせているので自然と陰ができて、それもまたありがたい。

▷先をゆく少年が見つけたカタツムリ。最近、平地ではあまり見なくなったと思う。
しばらくすると舗装道路から山道ヘ。
この辺りまで、クセでムシ眼になってしまいがちだったけれど、
よそ見をしていたら確実に転げ落ちるので早々にあきらめる。
それにしても、登山口にたくさんいた人たちの姿が全く見えない。
「あの人たちはどうしたんだろう…」と2人で首をひねる。
まあ、混んでないに越したことはないのだけれど。

▷登山中、最初から最後までずっと見られた植物。
コアジサイというアジサイのよう。可憐で山によく似合う。


▷もともと今回は「きっと暑いから滝でもみよう」という計画だったのだ。
この滝は見事だったなぁ。たたずまいも美しい。
なんというか、落下エネルギーの大半が風圧に変わっている感じで
近くへいくとすごい風だった。涼しくて気持ちよかった!

▷揺らぎがなければ水があるってわからないくらい透明。

▷道に落ちていたオオミズアオの前翅。付け根がふわふわだ。

▷そして苔はもさもさ。どうぶつの毛皮みたいだった。
途中に続く勾配にひーひー言いながらも、順調なペースで登って
およそ予定どおりに山頂に到着。
山頂が広めだったのでたくさんの人がお昼を食べている。
この頃から霧がかってきて、あいにく眺望は良くなかったけれどぼんやり見える遠景もなかなか。
ただ、服が絞れるくらい汗をかいていたので、じっとしていると急に寒くなり
これはいかんと、下山を開始。
すると少し前に、カラフルなご年配のパーティーが。
こ、これはあまりにも……と2人で「ハイホー、ハイホー」と思わず口ずさみつつ激写。

▷ハイホー、ハイホー。
そして進む道はこんな感じ(↓)になってきて、しっとりと静かだ。

…とこの辺までは写真も定期的にあるのだが以降、下山は予想だにしなかったサバイバル。写真どころじゃない。
メインではない登山道を選んで進んでみたら、けものみちもかくや…というほどにかそけき道で、
しかも左は斜面のうえ、両側からもっさりと植物が生い茂っているのでばっさばっさとかき分け進む。
やや不安にかられつつ行くと、ほそーーーい道のクサリ(ロープ)場。
ロープが設置されている=登山道というので若干安心はしたものの、違う意味で不安な道。
「うひょー!」「ぎゃー」といいながら超急勾配をロープを頼りに降りる。
連日の雨で足場も悪いので、
脳裏をS嬢の「生きて帰ってきてくださいねっ!(心配性)」という言葉が
妙にリアルによぎってしまった。
その後もここでいいんだろうか…と思わずにいられない道はえんえんと続き
いい加減、お互い「本当に登山道だろうな…」という想いがよぎった時、
天啓のように、向かいから中学生くらいの子たちのパーティーがやってくる。
先導する先生(多分)にKC嬢が道が合っているか確認したところ
「ああ、まだちょっと先だけどそうですよー」と答えが返ってきてホッと一息。
「あの子たち、あの道を登るのか……」と遠い目で見送ったところで、
雨が本格的になり出したので雨具装着。
背後から「きゃー」「わー」「ひゃー」と黄色い声が響き渡る。さもありなん…。
さらに進むとようやく標識に出会う。ほっ。
そこからドロドロにぬかるんだ細い道を黙々と下ったり登ったりして
もう2つのピークを踏む。いやはや。……いやはやー。
あとは下りに下る…が、これがまたすさまじかった!
滑らないように気をつけながら足下を見て黙々と下るのだが
ふと振り返ってみるとギョッとするような勾配。
結構な斜度を下りているんだな…と思っていたら、しばらくして見事に足にきた。
勢いで下りないと足が小刻みに震え始めるので歩みを止めないように気をつける。
しかもこの頃には雨は大振りになって全身びしょぬれ。
でも、こういう時あらためてギアの高機能っぷりに感心したりする。
雨具の下は全く雨が入ってこない。
それに、石も土も濡れて滑りやすい時は、
自分の登山靴をどれだけ信用できるかで下り方が随分違うなあと思った。
普段の靴の意識のままだと、「こんなところ絶対滑るな」と思ってしまうので
スムーズに下りれず、足も緊張して疲れるけれど
段々「あれ、もしかしてこれくらいでは滑らないのか…」とわかってくると
それにあわせた大胆な歩みになってくる。
普通の靴とは全く違って、想像以上に高性能なのだなあ。感心。
……
黙々黙々………。
もう脳は思考停止状態、機械化した身体。
ようやくようやく人家に辿り着いた!ところで「いやぁ…!」「いやぁ…!」とねぎらい合う。
なんというか、本当に「いやぁ…!」なのだ。
駅を出発してからここまで7時間30分。これまでで最長記録!
舗装道路になったもののそこからさらに2.3km歩いて駅方面へ。
でもキビシイ下りのあとだと舗装道路なんてどれだけ歩いても平気だ。
誰もいない道をひそひそ話をしながらのんびり歩く。
その後、待望の温泉で「うへー」と過ごす。
明日の足は使いものにならないことが確定。ぎしぎしだ。
あれこれと振り返りつつ休憩をして、雨上がりを帰路へ。
(もはやこの頃には「滝?ああ、そういえば見たね」くらいに遠い記憶)
電車の中も楽しくて、
ふたりの登山、というのも大変に濃密でよい時間でありました。
うふふのふー。
今回のルートはすごかったけれど、でもとにかく楽しかった。